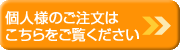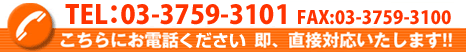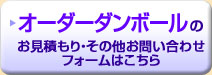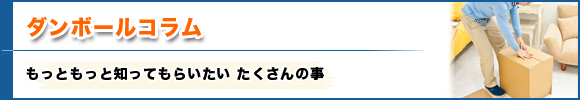
知っておきたい!ダンボールの強度と構造
ダンボールを選ぶ際、重要になるのが強度です。もちろん、サイズも大事ですが、ダンボールの強度が弱いと、輸送時に大変なことになります。最近はネット通販、フリマサイト・アプリの発展で、ダンボールに接する機会も多くなりました。そこで、ダンボールの強度や構造などの基本をお伝えします。

ダンボールの基本的な構造を解説
ダンボールの強度に関する知識を深める前に、まず基本的な構造を把握することが不可欠です。ダンボールのメカニズムを理解してこそ、仕組みが立体的に分かるようになります。構造的にはとてもシンプルなので、ぜひ頭の中に入れておいてください。
一般的にダンボールを構成しているのは、強度を保つため、主に3つの紙材からできた材料です。これを組み合わせて(張り合わせて、ダンボールが出来上がります。通常、市場に流通しているダンボールのほとんどが、このような構造体になります。
ダンボールを構成する材料
・表ライナー
・中芯(波型に加工したボール紙)
・裏ライナー
これら3つの材料を組み合わせて3層構造になっているのが、一般的なダンボールです。3つのどの材料もダンボールの強度を維持するために欠かせません。特に中芯は、ダンボールの強度にとって、最も重要な役割を果たします。
ライナーは、強度によって古紙含有率の比率を増減させています。古紙含有率が高けれは、ダンボールの強度が弱くなり、逆にバージンパルプでは強度が強くなります。当然、ダンボールのコストも強度が高まれば、上がっていきます。
ライナーの種類とは?
ダンボールの中芯を表裏で挟んでいるライナーは、非常に重要な役割を果たしています。ダンボールの強度を維持する中芯を守るのが、その大きな役目になります。外圧が直接、中芯に伝わることを防ぎ、保護するのが2枚のライナーの仕事です。
ライナーはダンボールの用途による強度差によって、材質が大きく異なります。菓子箱の仕切りに使用するダンボールは、強度が弱くてもかまいません。反対に引っ越し用のダンボールは一定の強度がなければなりません。
【ライナーの種類と用途別の利用法】※重さは1㎡あたり
C5=重さ160~180g
古紙含有率が90%以上。強度を必要としない薄手の洋服や軽量なバッグなど、軽量物を対象としたこん包用になります。このほか、仕切りやパットとしても活用されます。C6=重さ160~180g
古紙含有率が90%以上。C5に比べて若干、強度が上がります。しかし、C5との明確な強度の差異が少なく、K5で代用されることが主流になり、生産量が減っています。K5=重さ170~180g
古紙含有率50%以上。一般的な規格になります。通常のこん包から、引っ越しまで幅広く対応できます。Kはクラフトタイプの意味で、外部印刷もきれいに仕上がります。K6=重さ210~220g
古紙含有率50%以上。強度を必要とするタイプです。重量物にも対応できます。積み上げて収納しても、天面(上部)がつぶれにくいので、引っ越し用にも最適なタイプです。K7=重さ260~280g
古紙含有率50%以上。特殊形状や重量物、輸出用に主に利用されているタイプです。一般的にはあまり流通しておらず、製品などのこん包で専用に作るケースが多いです。フルートとその種類とは?
ダンボールの強度には、波型になった中芯が非常に重要な役割を果たします。さらに、強度を増すために中芯を重ねていきます。これによって、中芯に厚みができます。この厚みことをフルートと呼び、ダンボールの強度が決まっていきます。

【フルートの種類】
A段フルート=30cm内に波型が32~36個
厚さ5mm。一般的に利用されているダンボールがこのタイプです。野菜や果物の食品から引っ越しまで幅広く対応できます。B段フルート=30cm内に波型が48~52個
厚さ3mm。Aフルートより薄いため、小さな軽量物のこん包に最適。内箱をこん包する際の緩衝材にもなります。こちらも幅広い用途に適応します。C段フルート=30cm内に波型が38~42個
厚さ4mm。世界のグローバルスタンダードになっているタイプです。Aフルートより、厚さが1mm薄くなっています。それでいて、強度の差がほとんどありません。W段フルート
厚さ8mm。AフルートとBフルートを組み合わせて、強度を増加させたタイプです。精密機器などの輸出用に多く使われています。E段フルート=30cm内に波型が90~100個
厚さ1.5mm。波型が非常に細かく、段目も目立ちません。このため、パッケージやギフト用に利用されるケースが多くあります。使用する材質によって強度が変わる
ダンボールの強度は、表裏の両ライナーとフルートによって決まります。この2つの材質を巧みに組み合わせることによって、ダンボールの強度を確保しているのです。つまり、ライナーとフルートは関連性が強い材質になります。例えば「C5のライナー」+「B段フルート」では、最も強度の弱いダンボールになります。反対に「K7のライナー」+「W段フルート」の組み合わせが、ダンボールの強度が最も強くなります。なので、ライナーとフルートの関係は、とても重要になるのです。
ライナーとフルートの関係性をしっかり理解できれば、効率的で無駄のないこん包ができますよね。ダンボールの強度不足で、大事な商品や身の回り品が破損した、というような事態を防ぐことができます。
ダンボールの強度は用途に合わせた選択を
ライナーとフルートの関係が分かれば、用途に適したダンボールをチョイスすることができます。たいていの人は、ダンボールに大きさ以外の種類が存在することすら、把握していません。ダンボールの強度なんて、考えたこともないかと思います。
ただし、ダンボールは大切な身の回り品や商品を守ってくれる大切なアイテムの一つなのです。肝心なのは用途に応じて、最適な強度のダンボールを選ぶことです。こん包物とダンボールの強度を一致させることが必要です。例えば、季節外の衣類を自宅から実家に発送する場合は、A段フルートやC段フルートのダンボールが最適です。衣類は重量物ではないので、強度に関してあまりナーバスになる必要がありません。
しかし、同じ衣類でも海外の赴任先や留学先に発送する場合、事情が違ってきます。このケースではW段フルートのダンボールが最適です。特に海外では日本と違い、荷物をラフに扱うケースも多く、重量物を上に載せられるケースもあるからです。
ダンボールの強化を保つための注意点とは

ダンボールには、発送などに対応するため、統一された規格によるサイズを定めています。縦×横×高さの3辺の和によってサイズを決定します。重量にもよりますが、サイズによっても、発送などの料金が異なるケースがあります。重要なのはダンボールのサイズを把握していないと、荷物が入り切らず、無理に詰め込んで強度が下がることもあります。無理に荷物を押し込んで、ダンボールが膨らめば、それだけ強度が弱くなります。
ダンボールの強度を保つためにも、サイズの感覚を持って、詰め込み過ぎないことです。K7ライナーとW段フルートの最強の組み合わせでも、ダンボールを正しく使用しなければ強度を保つことができません。ダンボールにとって最大の敵ともいえるのが、水濡れです。引っ越し時、コンビニへ持ち込んで宅配便などを利用する時など、雨に濡れる可能もあります。濡れたダンボールは、フルートの波型が水分でつぶれてしまうなど、強度が一気に低下します。
一度濡れてしまったダンボールは、完全に乾燥させても元の強度に戻りません、フルートの波型が崩れてしまい、元の形に戻ることがないからです。こうなれば、保管用に利用する以外、発送では使用しない方が賢明といえます。
ダンボールのサイズと用途、強度の関係
ダンボールのサイズは、たくさんありますよね。アクセサリーを入れる小型タイプから、家電製品がすっぽり入る大型タイプまで、実にレパートリーの幅が広いですよね。例えば引っ越しで運送業者が持参するタイプでは100、120、140サイズが多いです。このサイズはあくまで大きさなので、強度を示す数値ではありません。この中で100サイズのダンボールが最も小さく、書籍などの形が統一された重量物に向いています。引っ越しなどでは通常、重量物の収納は小型サイズのダンボールを使います。
理屈的には重量物を大きなダンボールに入れると、強度のバラツキによって破損するケースがあります。小さなダンボールでは3辺の和が小さくなる分、それだけ密度が高まるので負荷を受け止めることができ、重量物のこん包に向いています。大きなダンボールは、いっぱい詰め込んでも1人で運べるような重量が目安になります。例えば衣類やタオルなどの軽量物、ぬいぐるみや造花など規格外の大きな品物などが対象になります。すき間に衣類やタオル類などを詰め、空間を空けないようにします。
【ダンボールの主な種類】※サイズは長さ×幅×深さ(高さ)
60サイズ=以下サイズ例
・264×194×114(mm)=3辺の和が60cm以内
80サイズ=以下サイズ例
・350×250×160(mm)=3辺の和が60cm以内
・370×260×130(mm)=3辺の和が60cm以内
100サイズ=以下サイズ例
・430×315×200(mm)=3辺の和が100cm以内
・405×280×240(mm)=3辺の和が100cm以内
120サイズ=以下サイズ例
>・500×355×275(mm)=3辺の和が120cm以内
140サイズ=以下サイズ例
・535×440×330(mm)=3辺の和が140cm以内
・550×400×270(mm)=3辺の和が140cm以内
まとめ
多くの人はダンボールの強度について、あまり真剣に考えたことがないかと思います。一番は対象物がしっかり入るかどうか、サイズに関する一点だけではないでしょうか。ダンボールの強度にはスポットがなかなか当たっていませんが、非常に重要です。1枚の紙材に見えたダンボールの中身が実は、複雑な構造になっており、荷物をしっかりガードする役割があります。そんな知識を多少なりとも身につければ、引っ越し時や荷物の発送などが非常にスムーズにいき、安心できますよね。